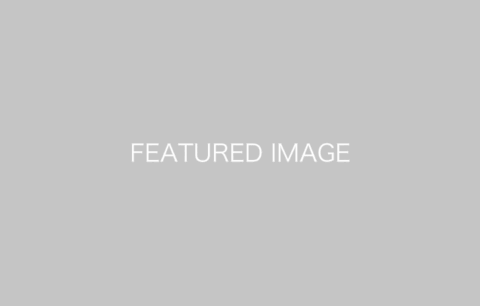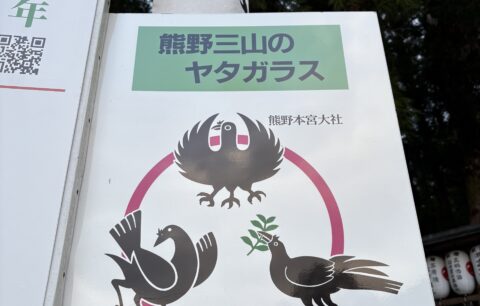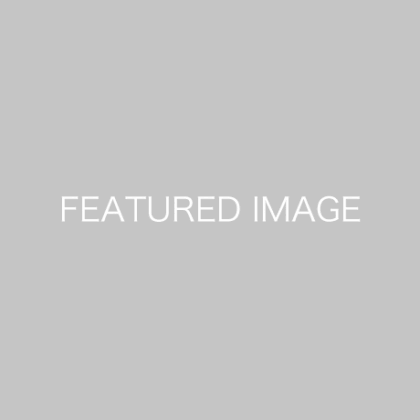生没年: 1878年(明治11年) – 1906年(明治39年)
出身地: 和歌山県那智勝浦町 浜ノ宮 (当時は東牟婁郡宇久井村)
中村覚之助(なかむら かくのすけ)は、日本サッカーの黎明期に大きな功績を残した人物で、「日本サッカーの父」とも呼ばれています。和歌山師範学校(現・和歌山大学教育学部)を卒業後、宇久井尋常高等小学校で教鞭を執りました。その後、東京高等師範学校(現・筑波大学)に入学し、在学中に「アッソシェーションフットボール」を編さんし、ア式蹴球部を創設しました。これが日本初のサッカーチームとされています。
単に最初にサッカーをやったのではなく、「教育」と「人格形成」を通じてサッカーを導入した先駆者でもあり、彼の活動があったからこそ、学校体育や部活動におけるサッカーが日本に根付く第一歩となりました。
少年時代と教育者としての第一歩
和歌山県の師範学校(現・和歌山大学教育学部)を卒業後、宇久井尋常高等小学校で教員として働き始めます。当時から教育に熱心で、欧米の教育思想に興味を持っていたと言われています。
1902年、東京高等師範学校(現・筑波大学)に入学。ここで、英国から導入された「アソシエーション・フットボール(=サッカー)」に出会います。
日本初のサッカーチームの設立、中村は、サッカーを「人格育成に役立つスポーツ」として捉え、学校内に「ア式蹴球部(あしきしゅうきゅうぶ)」を設立。これは日本初のサッカーチームとされており、今日の日本サッカーの原点とも言える出来事です。
教材「アッソシェーションフットボール」の編さん、自らサッカーのルールや戦術を日本語で解説した教材「アッソシェーションフットボール」を執筆。当時の日本にサッカーの専門書はほとんどなく、これが最初期のサッカー教本とされています。
1906年、わずか28歳の若さで病死。教育者・スポーツ指導者としての本格的な活動は短命に終わり、その後の日本サッカー界に直接関わることは叶いませんでしたが、彼の遺した教えや著作は後の世代に受け継がれました。その情熱と先見性は、後の日本サッカー界に多大な影響を与えたのです。
しかし、
彼の功績をたたえ、那智勝浦町には顕彰碑が建てられています。
和歌山県からは「県の先人」として正式に認定され、名誉町民の称号も授与されています。