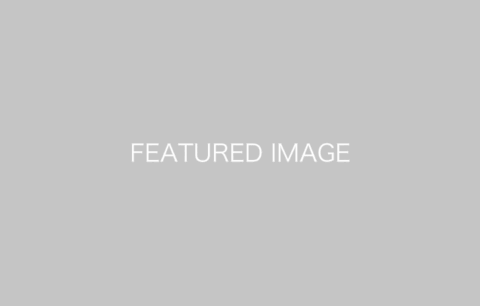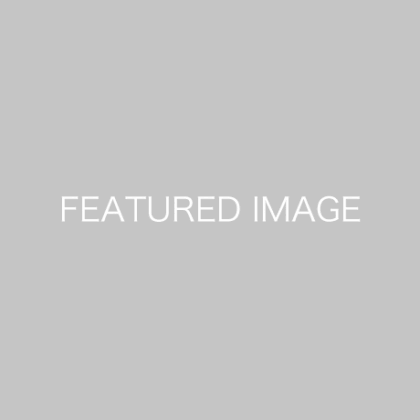御縣彦社(みあがたひこしゃ)は、熊野那智大社の境内にあり、熊野の神様のお使いである三本足の烏 八咫烏(やたがらす)をお祀りしています。
伝説とのつながり
『古事記』と『日本書紀』という古代の年代記によると、八咫烏は太陽の女神である天照大神の使いでした。八咫烏は、初代神武天皇を熊野から日本で最初の都が開かれた現在の奈良県に導くた
めに遣わされました。八咫烏という言葉は、「8 咫もあるカラス」という意味で、八咫烏が大きいことを表しています。『古事
記』と『日本書紀』ではその足については触れられていないものの、数世紀後の年代記や記録には、八咫烏は三本の足を持つと記されています。太陽と関連した三本足のカラスの伝説は、アジアの多くの地域に見られます。
熊野への帰還
天照大御神は熊野那智大社の祭神でもあることから、八咫烏は熊野の神々の使いとされています。また、八咫烏自体も神であり、導きの神として知られています。地域の伝承によると、八咫烏は神武天皇を奈良に導いた後、熊野に戻りました。くちばしを羽の下におさめて身を休めた八咫烏は、今でも熊野那智大社の境内に鎮座している八咫烏石へと姿を変えました。熊野那智大社が那智大滝からこの場所に遷されたのは、八咫烏がここに降り立ったためと伝えられています。八咫烏は熊野地方のシンボルとしてよく使われます。サッカーファンなら男女両方のサッカー日本代表チームのロゴマークとして八咫烏に見覚えがあるかもしれません。このロゴマークは勝浦出身の中村覚之助(1878-1906)にちなんで選ばれました。中村覚之助はサッカーのルールを初めて日本語に翻訳し、日本にサッカーを普及させるため献身的に活動しました。